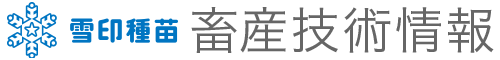| サイレージの二次発酵は、古くから問題視されていながら、いまだに現場で散見される課題です。サイロを密封している間は内部が嫌気状態のために、二次発酵の原因となる酵母やカビは眠っている状態ですが、開封して空気に触れることによって活動を開始して変敗が進みます。従って二次発酵対策は、サイレージへの空気の侵入や空気との接触をできるだけ少なくすることが基本です。
踏 圧 |
 |
| 中仕切り バンカーやスタックサイロでは、重機による踏圧になるので難しいと思いますが、塔型サイロや地下サイロなどでは、ビニールで中仕切りを行うことで二次発酵の進行を食い止めることができます。山形県畜産試験場によると、夏場でも7日分の取り出し量ごとに中仕切りを行うことで、品温の上昇やサイレージの廃棄を防止できると報告されています(以下のデータは地下サイロでの試験結果)。 |
 |
| 重 石 十勝北部農業改良普及センターでは、下図のようにロールを重石として使うことで、サイロ開封後に空気が中まで入り込まないようにする技術を紹介しています。踏圧作業が十分に出来ない場合、密封後からこのような重石をするのも一つの方法だと思います。 |
 |
| サイレージの取り出し方法 二次発酵はサイレージが空気に触れることによって始まります。従って、サイレージと空気が触れる時間を短くすることで、二次発酵が始まる前にサイレージを給与することが可能です。二次発酵の進行を遅らせるためにも、以下の点に注意しましょう。 ・サイレージの取り出し厚は、夏場であれば15~20cm以上確保しましょう。 ・上記の取り出し厚を確保するために、サイレージの給与量からサイロの間口を計算してサイ を設計しましょう。 ・夏場給与する分だけ、間口の小さい別のサイロ(スタックサイロなど)を作ることも有効です。 ・サイレージカッターやサイレージグラブを使いましょう。取り出し面が崩れないサイレージカッタ ーは、サイロへの空気の侵入が少ないので、二次発酵が進みにくくなります。 ・バケットで取り出す場合は、先端を使って上から下に削り落としましょう。 ・サイレージの取り出し面は、直射日光が当たらない方向にしましょう。サイロの設計上、直射 日光があたる場合には、反射シートなどで取り出し面の温度が上がらないようにしましょう。 |
 |
| サイロ見張番 当社では、サイロ開封後の二次発酵抑制資材として、「サイロ見張番」という商品を 販売しております。 二次発酵の原因となる酵母やカビは、サイロ開封前の嫌気条件の時は眠った状態ですが、サイロ開封後に空気が侵入すると活動を始めて、発熱や変敗を引き起こします。 サイロ見張番に含まれるカラシ油成分(アリルイソチオシアネート)により酵母やカビ の増殖を抑え、二次発酵による変敗を抑制します(右図)。 |
 |
| 下の図1は、実際に塔型サイロ(トウモロコシサイレージ)でサイロ見張番を使用したときの事例です。無処理の場合、取り出し直後に比べてその1日後にはサイレージのpHが急激に上がり、二次発酵による変敗が進んでいますが、サイロ見張番を処理することで、二次発酵が抑制されてpHの上昇が抑えられる傾向でした。 サイロ見張番が使用できるのは、塔型、タワー、地下、半地下タイプのサイロです。バンカー、スタック、トレンチサイロには効きにくいので注意して下さい。なおサイロ見張番に関する詳細は、当社の機関誌「牧草と園芸」51巻、3号をご覧下さい。当社のホームページから閲覧できます。 |
 |