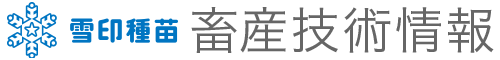|
標記の内容について12月上旬までの結果をまとめました。日々の仕事等に役立てて頂ければと思います。21年産1番草については、分析結果より考察すると下記のようなポイントがありそうです。 ○ 引続き低粗蛋白質、高繊維の傾向にあり、繊維消化性も悪い |
|
●乾草(1番草)の傾向 表1.乾草における5ヵ年の平均値推移 水分以外は乾物%
|
|
21年産チモシー主体混播草地の1番乾草の平均値(表1)を見ると,ここ4ヵ年は粗蛋白質が低く、OCW、ADFといった繊維が高い傾向が続いていますが、21年産は更に繊維、リグニンなども高く消化性も悪くなってきているかも知れません。また、ここ数年続いたテタニー比の高い傾向は収まってきています。刈遅れの他、肥料価格高騰、適正な施肥や糞尿を活用した減肥などの影響かもしれません。 |
 |
 |
|
●牧草サイレージ(細切)の傾向 表2.牧草サイレージにおける5ヵ年の平均値推移 水分,pH以外は乾物%
|
| 21年産牧草サイレージでも低粗蛋白質、高繊維といったここ数年の傾向は引き続いており、更に高繊維の傾向が強いようです(表2)。 OCWの分布を見てみると、70~75%の割合がここ3ヵ年で一番高いことが分かります(図3)。また、21年産TDNについては、例年分布の中心となるTDN58~60ではなく、TDN56~58が分布の中心となっています(図4)。NFCでも若干低いようで、5~15%の割合が例年より若干多いようです(図5)。 テタニー比が高い傾向は収まってきておりますが、関係する元素それぞれが例年に比べ低くなっています。カルシウムやマグネシウムの減少はテタニー比を上げる要因となるので注意下さい。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 21年産サイレージの有機酸を見ていくと、例年に比べて生成される有機酸の量が少ないことが分かります(表3、図9)。通常サイレージ有機酸の大半を占める乳酸においても、同様な傾向が見られます(図10)。そのため、サイレージのpH3.8以下のものが例年の半分程度になっているのが分かります(図11)。V-Scoreの平均値や分布を見ると昨年度と差があまり見られません(表3、図12)。サイレージ品質が若干改善傾向にあるように思えますが、含量の少なかった乳酸はV-Scoreでは評価に含まないため、悪化傾向にはないかもしれませんが、品質が改善傾向にあるかははっきりしません。むしろ、きちんとした乳酸発酵がされていないサイレージが増えてきているのかもしれません。 |
 |
 |
 |
 |
|
表3.牧草サイレージにおける5ヵ年の発酵品質平均値推移
|
| 各地区別に見ても低粗蛋白質、高繊維の傾向は共通して見られるようです。その中でもOb/OCW%では道央地区が非常に高い傾向に、リグニンでは道央地区だけでなく北見地区でも高い傾向が見られています。 |
|
表4.各地区の牧草サイレージの平均値 水分,pH以外は乾物%
道央は札幌,苫小牧,旭川 |
|
●ラップサイレージの傾向 表5.ラップサイレージにおける5ヵ年の平均値 水分,pH以外は乾物%
|
| ラップサイレージの傾向も乾草、牧草サイレージ(細切)と同様に低粗蛋白質、高繊維の傾向にあり、OCWやリグニンはここ数年で一番高い結果となっています(表5)。OCWの分布を見てみると、分布の中心が例年よりOCW70~75%の割合が非常に高くなっていることが分かります(図13)。また、その影響はNFCにも表れ、NFCが10~15%の割合が高く、21年産の分布が例年より低いことが分かります(図14)。 |
 |
 |
| ラップサイレージも、牧草サイレージ(細切)同様に道央地区、北見地区で高繊維傾向にあり、Ob/OCW%やリグニンが高く繊維消化性が悪い傾向を示しています。これら地区ではTDNも他地区よりも低い傾向にあります(表6)。 |
|
表6.各地区のラップサイレージの平均値 水分,pH以外は乾物%
道央は札幌,苫小牧,旭川 |
|
●まとめ |